「お、重たい…」
まだ森の中程だというのに、リューイは既にくたくたになっていました。一歩、踏み出すごとに背中に背負ったベニーの重みも増すようです。リュックの肩紐が肩に食い込んで痛くて仕方がありません。虫カゴは既にトンボやバッタ、コオロギ、チョウなどの昆虫で一杯になっていました。お母さんから渡されたカゴにも、キノコや森イチゴや木の実がたくさん入っています。
「はぁ…重たい。欲張るんじゃなかった…」
リューイは荷物を全部、投げだしたい衝動に駆られました。おあばちゃんの家はまだ先ですし、昨日、なくしたお母さんのカゴも探さなければなりません。
――どこでなくしたのかなぁ
リューイは一生懸命、記憶の糸を手繰りました。昨日は珍しく道草もせず、真面目にお遣いをしていたのです。そうです、珍しく真面目に。途中でミュウミュウという鳴き声を聞くまでは……ミュウミュウという……
「思い出したっ!あそこだ!」
リューイは大声で叫ぶと、勢い良く駆け出しました。走るリューイの背中で重たいリュックが左右に大きく揺れ、それに連れてリューイの細い体も左右に振られます。
リューイは記憶を辿りながら、今来た道を戻り始めました。目指すは昨日の小川です。やがて前方から風に乗って水の匂いがしていきました。小川が近いに違いありません。
程なくして、リューイは昨日の小川へと辿り着きました。辺りを見回すと、黄色い花の中に埋もれるようにして、カゴが落ちていました。カゴの中に入っていたたくさんの食べ物は、ほとんどなくなっており、くるみパンが一つ残っているだけでした。森の動物たちが美味しく食べたのかもしれません。
リューイは手に持っていた荷物をすべてカゴの横に置くと、背中のリュックも降ろすことにしました。荷物が多すぎて、もう限界です。
「ふぅ~、重いよ、ベニー…」
リューイは地面にリュックを降ろすと、ベニーに文句を言いました。勝手に連れてきておいて文句を言うなんてあんまりですが、ベニーは気にする様子もなくリュックからゆっくりと出てくると、う~んと前脚を伸ばし、次に後脚を一本ずつピーンと伸ばしました。それからもの珍しそうに辺りを見回すと、周囲にある物すべての匂いを一つ一つ入念にチェックしなら、一歩一歩慎重に歩き出しました。夢中で匂いを嗅ぐあまり、うっかり後脚でチャワン草を踏んでしまうほどでした。チャワン草はその名の通り茶碗のような形をした花で、その中に朝露が溜まっていたのでしょうか。ベニーは濡れた前脚を厭そうに振りました。
水面を渡る涼しい風が、木々の葉をさわさわと揺らします。
「はあ~」
リューイは柔らかい草の上に大の字に寝そべると、森の空気を胸いっぱいに吸いこみました。透き通った水の中を泳ぐ魚の群れがキラキラと光を反射して泳いでいきました。
リューイたちが座っている辺りは、小川が緩いカーブを描いており、小川に縁に生えている大きな木が川の上に陰を落としていました。その陰の中や水草の中が魚たちの絶好の隠れ家になっているようでした。水も浅過ぎず、深過ぎず、草舟を浮かべて流したり、水車を回して遊ぶのにもってこいの場所でした。
――今度はここに遊びにこようっと!
こんな良いお天気の日に水遊びができないのはとっても残念ですが、今日はカゴを回収したら真っすぐにおばあちゃんの家に行かないといけません。
――でも、少しだけならいいかな? ……う~ん、ダメダメ!
リューイが水遊びをしたい気持ちを懸命に抑えていると、どこからかともなく、不思議な小さな音が聞こえてきました。虫の羽音のようにも聞こえますが、小さな話し声のようにも聞こえます。声が小さすぎてよく聞き取れません。
――なに、この声?虫? 虫がしゃべってる?!
リューイがじっと耳を澄ましていると、その声はだんだんリューイたちのほうに近づいてくるようでした。どうやら向こうはリューイたちに気が付いていないようです。リューイは急いで身を屈めると、草むらに身を隠しました。リューイたちが草むらの中でじっと息を潜めていると、やがて小さな生き物が二匹、飛んできてカゴの縁にとまりました。
リューイは最初、それを虫だと思いました。しかし、よく観察してみるとそれは虫などではなく、小さな人間でした。いいえ、正確には羽が生えた小さな人間でした。虫のような人間たちは、葉っぱを幾重にも重ねたスカートを穿いており、ウエストの周りに蔦を巻いて葉っぱを留めていました。細くて背の高いほうは、緑色の葉で作ったドレスを着て、頭には白い花で編んだ花輪を載せていました。もう一人のほうは背が低く、少し太っちょで、白い葉っぱでできたスカートを穿いて、小さなピンクの花のネックレスを付けていました。
「ベニー、あれはきっと妖精だよ。」
リューイは小さな声でベニーに囁きました。リューイもベニーも妖精なんて見るのは初めてです。ベニーは目の前の光景に、知らない場所に連れてこられた警戒感も一気に吹き飛んだらしく、目を爛々と輝かせて目の前で動き回る不思議な生き物を見つめています。ベニーはそっとリューイに腕の中から抜け出すと、頭を低くしてお尻をフリフリと振り始めました。
「ベニー、ダメだよ。」
リューイは声を潜めて、ベニーを抱きかかえました。
じっと見守る二人の前で、妖精たちはカゴの中を覗き込みながらなにやら話しこんでいます。風に乗って聞こえてくる二人の会話を、リューイは少しだけ聞き取りことができました。
「やだ、なに、これ〇×△…」
「…食べ物よ!」
誰かが自分たちの会話を聞いているとは、夢にも思ってもいない様子です。
「それにしても、……がいないわ。」
「誰かに…」
――「…がいない」って、の赤ちゃん竜のことを言っているのかな? この人たち、赤ちゃんドラゴンについて、何か知っているのかな?
リューイは二人に声を掛けたくなりましたが、突然、姿を現したらきっと驚いて飛び去ってしまうに違いありません。リューイはもう少し二人を観察することにしました。
「せ~の~!」
「う~ん、重い…」
「無理だわ…」
どうやら妖精たちはくるみパンを持ち帰ることに決めたようです。先程から彼是、5分ほどもくるみパンと格闘しています。二人は力を合わせてくるみパンを持ち上げようとしていますが、妖精たちにはかなり重いようで、なかなか持ち上がりません。
ずっと同じ姿勢で見ていたリューイは、いい加減、足が痺れてきました。リューイは二人がくるみパンに気を取られている隙に、そっと体勢を変えることにしました。リューイは音をさせないように、片脚ずつそっと動かしました。うっかり木の枝を踏みつけて音をさせることがないように、足下にも気を遣います。
そのときです。前方から「キャー」という悲鳴が聞こえてきました。
リューイが顔を上げると、白いドレスを着ているほうの妖精がベニーの口に咥えられていました。「離しなさい、このバカ猫!」
ベニーの頭をもう一人の妖精がポカスカ叩いています。大きな猫に向かっていくなんて、なんと勇敢な妖精でしょう。リューイは妖精の勇気に感心しましたが、感心している場合ではありません。
「ベニー!」
リューイは草むらから飛び出しました。
「キャアッ!」
ベニーの頭を叩いていた妖精は、リューイのいきなりの登場に死ぬほど驚いて、空高く舞い上がりました。
「ベニーっ、だめっ!妖精さんを離してっ!」
リューイは慌ててベニーの腰を掴みましたが、ベニーは怒られる理由がわからないのか、逃げる様子もなく、妖精を口に咥えたまま、誇らしげにゆっくりと振り返りました。しかし、リューイがせっかくの獲物を取り上げようとしているとわかると、今度は憤慨して座り込み、前足で妖精を抱え込んでしまいました。
これでは手の出しようがありません。無理に助け出そうとすれば、妖精を傷付けてしまいかねせん。リューイが何とか妖精を助け出そうとしている間、もう一人の妖精はリューイの頭を叩いたり蹴ったりしています。
小さな妖精に叩かれてもさほど痛くはありませんでしたが、それでも妖精の蹴りが目に入ったときはさすがに痛くて、思わず手で払い除けてしまいました。リューイに払い除けられた妖精は、あっという間に10メートルほど先まで飛んでいきました。
「妖精さんっ!ごめんねっ!」
リューイは飛んでいく妖精に謝りましたが、果たして妖精の耳に届いたかどうか。
ベニーはものすごい勢いで飛んでいくもう一人の妖精をキラキラした瞳で見詰めていましたが、その間ももう一人の妖精を前脚でしっかりと押さつけておくことを忘れませんでした。
リューイはどうしていいかわからず、困り果ててましたが、ふと何かを思いついたように辺りをキョロキョロと見回し始めました。振り返ると、少し先のほうに虫カゴが落ちていました。
リューイは虫カゴを拾いあげると、ベニーの目の前で開けました。中に入っていた虫たちは暫くじっとしていましがた、やがて次々と外に飛び出してきました。
ベニーはそれを見ると思わず立ち上がり、口に咥えていた妖精をポトリと落としました。
「今だっ!」
リューイはすかさず妖精を拾い上げると、ベニーに取られないように両手の中に包み込みました。妖精は気を失っているようでしたが、怪我はしていないようです。
そこへ先程、リューイに吹き飛ばされた妖精が戻ってきました。
「キキを離しなさい!この、悪党!」
妖精は再び、リューイの頭をポカスカ叩き始めました。リューイは目を蹴られないように背中を向けながら、叫びました。
「やめてよ、妖精さん!僕は何もしないよ!」
「嘘ばっかり!人間はいつも酷いことばかりしてきたっ!人間なんて信じない!」
妖精はリューイの言葉など聞いてはいません。
「待って!待ってよ、妖精さんっ!僕の話しを聞いて!僕は妖精さんと話しがしたいだけなんだから。」
「嘘つき!私たちを捕まえて虫カゴに閉じ込めるつもりなんでしょう!」
「違うよ!虫カゴになんか入れたりしないよ!ぼくは妖精さんとお友達になりたいだけなんだ。」リューイが無意識に叫んだ言葉には真実の響きがありました。妖精はふと、リューイを殴るのを止めると、ちょっと離れたところからリューイをしげしげと観察しました。落ち着いて見てみると、子供は正直で良い心を持っているように見えました。
妖精が静かになったのをみて、リューイがおずおずと口を開きました。
「この妖精さんは、キキっていうんだね。びっくりして気を失っているけど、怪我はしてないみたいだよ。」
リューイはそっと手の平を開けてみせました。
「そ… …そうなの?」
もう一人の妖精は恐る恐るリューイに近づくと、手の中を覗き込みました。
「……う……ん……」
ちょうどそのときです。キキと呼ばれた妖精がリューイの手の中で意識を取り戻しました。そして目を開けた途端、目の前に人間の大きな顔が迫っているに気が付き、再び気を失いそうになりました。
「…ああ…」
「ちょっと!気絶している場合じゃないわよっ!」
もう一人の妖精は、キキの手を掴むと、上へと引っ張り上げました。
「早くっ! 逃げなきゃ!」
キキは気力を振り絞ってリューイの手の中で立ち上がると、フラフラと飛び立ちました。
「キキ、大丈夫?」
「だ、大丈夫よ。」
「じゃあ、早くっ!」
二人は一刻も早くここから立ち去りたいようです。
「妖精さん、大丈夫?」
リューイは二人の妖精に向かって叫びましたが、返事は返ってきませんでした。
「さようなら~。僕は森の中のおばあちゃん家にいるよ。美味しいクッキーがあるから、いつでも遊びに来てね!」
リューイは遠ざかっていく二人に尚も話し掛けました。しかし、返事はありませんでした。
「あのね、昨日ね、僕、ここで赤ちゃんドラゴンを拾ったんだよ!ねえ、聞いている?」
リューイの声は空中に虚しく響き、妖精たちの姿はもうどこにもありませんでした。


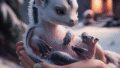

コメント