「許せませんっ!もう限界ですっ!森に返してらっしゃいっ!」
とうとう二人は外に放り出されてしまいました。時刻は既に夜の7時を回っていました。こんな時間にミュウを連れて森に行くなんて無理です。
「お母さん、ごめんなさいっ!ごめんなさいっ!入れてよっ!中に入れてよっ!」
リューイは玄関のドアを叩きながら大声で叫び続けました。しかし、いくら叫んでもドアは開きませんでした。リューイの声にあちらこちらの家のカーテンが少しだけ開けられました。きっと近所の人はリューイが悪い事をしたと思っていることでしょう。
二人は長いこと玄関の前に座り込んでドアが開けられるのを待っていました。しかしどれだけ待っても、ドアが開く気配はありませんでした。
いくら待っても中に入れてもらえないと悟ったリューイとミュウは、トボトボと森へ向かって歩き出しました。ミュウともう会えないと思うと胸がキュッと痛くなりました。涙で曇って、前がよく見えません。ミュウはうなだれたまま、リューイの後に従いました。
夜の森は想像以上に真っ暗でした。リューイもミュウも夜の森に来たのは初めてでしたので、夜の森がこんなにも恐ろしいとは思いませんでした。森の奥へと続く歩き慣れた道も、今は暗いダンジョンに続く道のように思えます。この中に入っていくなんて、考えただけでもぞっとします。
「ミュウ、お母さん、すっごく怒っていたぞ。あんなに怒られたの初めてだよ… ミュウが悪いんだからな。」
「クー」
「いつも、いつも、いたずらばっかりして。なんで、おまえはそうなんだよ。せっかく、お母さんが家で飼ってもいいって言ってくれたのに…」
「クー…」
リューイは拳でゴシゴシと目を擦りました。
「もう、どうしていいかわからないよ…」
「ク…」
「もう一緒には暮らせないんだからな…森へ行ったら一人でちゃんと生きていくんだぞ…誰もおまえのことを…」
リューイは最後まで言葉を続けることができず、しゃくり上げてしまいました。リューイにとってミュウはただのペットではなく、大切な家族であり、相棒であり、友達であり、弟分でした。「はい、さようなら」なんて簡単に捨てられるわけがありません。
「ひっく、ひっく」
「ク…」
ミュウは慰めるようにリューイの顔を舐めました。
「やめろよ。」
リューイはミュウの顔を押しやりましたが、それでもミュウはリューイの顔を舐めることを止めません。
「バカ、ミュウ…」
リューイはミュウの首に抱きつくと、しばらくそのままでいました。
しかし、いつまでもそうしているわけにもいきません。季節は既に秋から冬へ変わろうとしてしました。振り返ると町は暖かな灯り包まれているというのに、森の中は真っ暗で寒々としていました。こんな暗い森の中でミュウが一人で眠れるのでしょうか。リューイはミュウを一人置き去りにすることはできませんでした。
「ミュウ、このまま二人で家出しちゃおうか。そしたら、ずっと一緒にいられるよ。」
「クー?」
ミュウは首を傾げました。「家出」の意味がわからないようです。
二人で森で暮らせば、もう毎日、叱られなくてすみます。リューイは森の中の生活を想像してみました。とりあえず、今夜、寝る場所を探さなければなりません。食べ物も必要です。木の実や野イチゴは簡単に集めることができるでしょう。小川に行けば水もありますし、魚だって採れます。木の枝を集めて火をおこせば、魚を焼くこともできます。川の水で体だって洗えます。たぶん、ちょっと寒いけど…
そこまで考えて、リューイは悲しくなりました。お母さんさえ家に入れてくれれば、食べ物もいっぱいあって、柔らかいベッドで眠れて、暖かくて、何よりも怖い思いなんてしなくてすむのです。
「僕たちが帰らなかったら、お母さんは泣くかな?」
リューイは力なく呟きました。
――それとも、フューイのお世話で忙しくて、僕のことなんて思い出しもしないかな?
そこまで考えて、ブワッと新たな涙が溢れました。
しかし、ここで引き返すわけには行きません。リューイとミュウはとりあえず一夜を過ごせそうな場所を探して、暗い森の中へと入って行きました。
不幸中の幸いとでもいいましょうか、ほどなくして、二人は大きな木の洞を見つけました。体を丸めれば二人が一緒に入れそうです。元々は野生動物の巣だったのでしょうか。洞の中には白っぽい毛の塊も落ちています。落ち葉もたくさん敷き詰められていました。手で触ってみると、落ち葉は冷たく湿っていました。どうやら、この巣の主はとうの昔にここを出て行ったようです。リューイは顔を顰めながら、ジメジメした落ち葉を手で掻き出しました。落ち葉の下には虫が潜んでいるような気がしましたが、暗くてよく見えませんでした。
――この中で寝るの嫌だな…
しかし、他に選択肢がありません。リューイは暗い洞の中をじっと見つめました。リューイが迷っていると、手の甲に何か違和感を感じました。ふと、視線を落とすと、手の上を黒いものがモゾモゾと這っていました。
「ギャアー!」
リューイは思わず叫んで、手をブンブンと振り回しました。リューイの大きな声にミュウがビクッと飛び上がります。
「ううっ…」
虫はどこかへ飛んでいきましたが、まだ手の甲にムズムズとした感触が残っています。リューイは何度もズボンに手を擦りつけました。
――この中に棲んでいる虫はあれ一匹じゃないよな…?いったい、どれくらいいるんだろう…
そう考えただけで、体中を虫が這い回っているような気分になります。リューイは思わず身震いしました。再び泣きそうになったリューイは、ぶんぶんと頭を振って、嫌な考えを追いました。この落ち葉を全部、掻き出さないことには、安心して中に入れません。リューイは涙を堪えながら、落ち葉を全部、掻き出しました。寒さと涙を堪えているせいで、鼻水が垂れてきます。
やっとのことで落ち葉を全部、掻き出すと、リューイは嫌がるミュウのお尻を押して洞の中に入りました。風が入ってこないせいか、洞の中はも暖かく感じられました。まだ、足元で何かが蠢いているような気がして落ち着きませんが、今晩はここで夜を明かすしかありません。
ウォォォーン
しばらくすると、どこからともなく狼の遠吠えが聞こえてきました。
ウォォォーン
ウォォォーン
あちらこちらで遠吠えに応える声も聞こえます。
これは間違いなく銀色狼でしょう。銀色狼はセントバーナードの二倍くらいの大きさがあります。人間の子供なんてペロリと食べられてしまうでしょう。それどころか、まだ鱗が柔らかいミュウだって、頭からバリバリと食べてしまうかもしれません。ミュウも本能的に危険を察知したのか、ガタガタと震え始めました。目には涙も浮かんでいます。
「泣きたいのはこっちだよ、ミュウ。」
リューイは泣きたい気持ちをぐっと堪えて、ミュウをギュッと抱きしめました。
「大丈夫だよ。僕がついているよ。」
―― ミュウは… ミュウはドラゴンだけど、弱虫だから。僕はお兄ちゃんだから…僕がしっかりしなくちゃ。
「ミュウ、大丈夫だよ。朝になれば…」
朝になれば、いつもどおり、明るい気持ちのよい森に戻るはずです。しかし、こんなにも真っ暗な闇を、リューイは知りませんでした。目の前にかざした手ですら見えないのです。この闇の中ではミュウの光る眼でさえも不気味に感じてしまいます。何もかもが異質で恐ろしく感じられる夜の闇の中で、二人は身を寄せ合って震えていました。ミュウは頼りにならないので、何かあったら自分が銀色狼と闘わなければなりません。二人でいるのに、一人で闘っている気分でした。

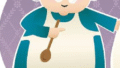

コメント