リューイと男の人がおばあちゃんの家に帰ってみると、二人の妖精たちはちゃっかりおばあちゃんお手製クッキーをご馳走になっているところでした。
「キキ!リン!こんなところにいたのか!」
自分の家のように寛いでいる妖精たちを見て、男の人は呆れたように言いました。
「あら、よくここがわかったわね。」
妖精たちはちらっと男の人を見ましたが、すぐに興味なさそうに視線をクッキーに戻しました。どうやら、三人は知り合いのようです。
「あら、大変!どなたか存知ませんが、ずぶ濡れじゃありませんか。そんなところに立ってないで、さあ、さあ、早く中に入って!」
おばあちゃんは戸口に立っている男の人を見ると、迷わず部屋の中に招き入れました。
「今、タオルを持ってきますから、そこに待っていてくださいね。」
男の人は、一瞬、迷ったようでしたが、リューイがテーブルまで手を引いて行くと、遠慮しつつも椅子に腰を下ろしました。
「ねえ、小母さま。小母さまの焼いたクッキーって本当に美味しいですわね。食べ始めたら止まらなくなってしまいましたことよ。お代わりをいただいてもよろしいかしら?」
妖精たちは男の人には構わず、澄ましておばあちゃんにクッキーのお代わりを要求しました。二人とも口調まで変わっています。おばあちゃんは妖精たちにクッキーを褒められると相好を崩しました。
「はい、はい、リンちゃん、キキちゃん、わかりましたよ。タオルと一緒にクッキーのお代わりも持ってきましょうね。」
男の人が呆れたようにいいました。
「おい、キキ、リン、ちょっと図々し過ぎやしないか。」
男の人が二人を窘めると、二人はそっぽを向きました。
「余計なお世話よ。」
「そうよ、私たちは小母さまと友達になったんだから。」
三人の会話を聞いたおばあちゃんは、ちょっと驚いたようでした。
「あら、三人はお知り合いなの?世の中、狭いわね。」
リューイも男の人が妖精たちの知り合いだと知って驚きました。
「キキちゃんとリンちゃんのお友達なら尚のこと歓迎しますわ。どうぞ、どうぞ、遠慮せずに座ってくださいな。」
リューイが出掛けている間に妖精たちとおばあちゃんは随分、仲良しになったようでした。
期待と感謝に満ちた目でおばあちゃんを見送ると、妖精たちはクッキー談義に花を咲かせました。「わたし、このレモンクッキーが気に入ったわ。」
「わたしはレーズンが入っているほうが好き。」
「チョコレートクリームを挟んであるのも美味しいわね。」
「二人とも随分とご機嫌じゃないか。」
男の人が揶揄うと、妖精たちはつんと澄ましました。
「それはそうよ。わたしたち、ずっと誰かさんの不味い手料理しか食べさせてもらえなかったんだから。甘い物なんて何ヶ月ぶりかしら。」
「そうよ、そうよ。誰かさんの不味い手料理とは大違いだわ。私たちがあまりにも酷い物しか食べていないのを知って、小母さまは私たちのために何かご馳走を作ってくれるって約束してくれたわ。ホホホホ。」
二人は勝ち誇ったように笑いました。食べ物の恨みは、恐ろしいものです。二人の言葉に男の人はただ肩を竦めるばかりでした。
実際、妖精たちは非常に良い気分でした。その理由の一つは、妖精族が甘い物に目がない種族であること。もう一つの理由は、二人がこれまで頑なに人間を避けていたせいで、このような歓待が初めてだったことです。二人にはクッキーという美味しい食べ物があって、ニコニコと話しを聞いてくれる優しいおばあさんがいるこの家が、とても心地良く感じられました。そんなわけで、妖精たちは心密かにまたこの家を訪ねてこようと決めていました。
「それにしても、このクッキー本当に美味しいわね。これを女王様に食べさせてあげたら、きっと元気になるのにね。」
「キキ!リン!」
男の人は、咳払いをすると、妖精たちにそれ以上しゃべらないようにと目配せしました。
しかし、妖精たちは男の人の目配せなど気にする様子もありませんでした。
「あら、何を焦っているの?」
「もう遅いわよ。だって、私たち全部しゃべってしまったもの。」
「!」
男の人はリンの発言にかなりの衝撃を受けたようでした。リューイは男の人の頭上に、一瞬、「!」マークが見えたような気がしました。男の人は何ことかを呟くと、両手で頭を押さえました。
妖精たちはおばあちゃんに何をどこまで話したのでしょうか。どうしたら、二人組のおしゃべりを止められるでしょうか。男の人が目紛しく頭を働かせていると、リンと言われたほうの妖精が男の人にこう言いました。
「怒ってばかりいないで、少しは私たちに感謝してもらいたいわね。私たちがあの子がここに居るのを見つけたのよ!」
「!」
男の人は再び驚きました。それもそのはずです。偶然、助けた男の子の家に赤ちゃんドラゴンがいるなんて、これが神様の計らいでなくてなんでしょう。男の人は思わずその場に跪いて感謝の祈りを奉げそうになりました。
そうこうしているうちに、おばあちゃんがタオルとクッキーを持って皆のところに戻ってきました。おばあちゃんは男の人にタオルを渡すと、クッキーが入った小皿を妖精たちの前に置きました。妖精たちが食べ易いように、クッキーは細かく砕かれていました。リューイと男の人の前には、砕いていないクッキーが置かれました。
男の人は礼を言ってタオルを受け取ると、まだ濡れている髪をわしわしと拭き始めました。一瞬、隠れていた顔が露わになり、額から右目に走る大きな傷が見えました。右目は閉じれおり、完全に失明しているようです。
「あっ!」
その傷を見たリューイは、思わず声を挙げてしまいました。すぐに口を塞ぎましたが、きっと聞こえてしまったに違いありません。
リューイがそっと男の人を窺うと、男の人は気にする様子もなく髪を拭き続けていました。顔半分は既に髪で覆われており、傷は見えなくなっていました。おばあちゃんも見ていたはずですが、おばあちゃんは何事もなかったような顔をしていました。
ややあって衝撃から立ち直ると、リューイはおばあちゃんにベニーが木の上から降りられなくなっていたこと、川に落ちて溺れそうになったこと、男の人がベニーを助けてくれたことなどを話して聞かせました。
ベニーはいつの間にかグルグル巻きにされた上着から抜け出して、部屋の隅で熱心に毛を乾かしていました。
おばあちゃんが男の人にお礼を言うと、男の人は当然のことをしたまでですと答えました。そして、自分はユストという名の旅の軍人であること、妖精たちと竜の子と一緒に旅を続けたきたことなどを話し始めました。
「申し遅れましたが、私は青の国の女王の側近で、ユストと申します。女王の命を受けて、ある目的の下に彼を連れてずっと旅して参りました。今し方、この者たちに聞いたところによると、彼はこちらでお世話になっているとか。」
「ええっ!あの子のことも知ってるのっ!」
リューイは驚きました。
「ええ、ええ、おりますとも。こんな偶然ってあるものなんですね。あの子のことまでご存知だなんて。」
おばあちゃんが嬉しそうに頷くと、ユストと名乗った男の人は立ち上がって、ドラゴンの子を見せて欲しいと言いました。
「あの子はずっと何も食べてなかったのですよ。随分、弱っているところを、この二人に助けてもらったんです。」
おばあちゃんはクローゼットの扉を開けながら、ユストにそう説明しました。

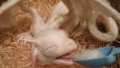

コメント