「妖精さん!」
リューイは妖精たちを見つけると、窓辺に駆け寄りました。
「気が付くの遅い!早く気付いてよ!」
「ねえ、あの子は大丈夫なの?」
リューイが窓を開けると、妖精たちは口ぐちに叫びながら飛び込んできました。何かを早口で捲くし立てているのですが、二人で同ときに話すものですから、リューイにはほとんど聞き取れませんでした。ただ、なんとなく自分が二人に非難されているということだけはわかりました。それでも、あんなふうに別れた後だけに、リューイは二人が訪ねて来てくれたことを嬉しく思いました。「妖精さん!よく来てくれたね!」
リューイは手を広げて、歓迎しました。リューイの歓迎ぶりに、二人は一瞬、言葉に詰まりましたが、すぐに気を取り直して、「遊びに来たんじゃないわ」とつんと肩をそびやかしましたが、それでもまだ何か言いたいことがあるらしく、二人はリューイの手の上に乗ってきました。
「ねえ、あの子は大丈夫なの?!」
「まさか、あなたが拾ったとはね!」
またしても、二人、同時にしゃべります。
「それがね……あんまり元気じゃないんだ。」
リューイは口籠りました。
リューイが部屋の奥に目をやると、おばあちゃんが赤ちゃんドラゴンの入ったカゴを抱えて、出てくるところでした。おばあちゃんは平静を装っていましたが、その目は大きく見開かれており、非常に驚いていることが見てとれました。ただでさえ丸い目が、さらに真ん丸になっています。
――まさか、この森に妖精が棲んでいたとは思わなかったわ。しかも、リューイと友達だなんて…おばあちゃんは静かに近づいてくると、妖精たちを驚かさないようにテーブルの上にそっとカゴを置きました。妖精たちはカゴの上を心配そうに飛んでいましたが、布は掛けたままでしたので、中を見ることはできませんでした。
「こんにちは、妖精さん。」
おばあちゃんが話し掛けると、二人は素直に返事をしました。
「こんにちは。」
「こんにちは。」
「あなたたちはこの子のことを知っているのね。この子について、あなたたちが知っていることを教えてくれないかしら。この子は昨日から何も食べていなくて、見てのとおりかなり弱っているのよ。このままでは、死んでしまうかもしれないわ。こんなときにあなたたちが現れるなんて、きっと天の助けだと思うわ。あなたたちはこの子が何を食べるか知っている?」
おばあちゃんが二人に訊ねると、二人は驚いたように顔を見合わせました。
「うそっ?!」
「ホント?!」
何が「うそ」で、何が「ホント」なのでしょうか。今度はリューイとおばあちゃんが、顔を見合わせました。
「そんなことも知らないの?」
痩せたほうの妖精が言うと、丸い頬をした妖精も本当だと言わんばかりに頷きます。
「私たちの国では、そんな事、子供だって知っているわよ。」
――「そんな事」って… 初めてドラゴンを見たんだぞ!ドラゴンが何を食べるかなんて分かるわけないだろ…
リューイはむっとしましたが、ここで言い返すのは得策ではないと思い、ぐっと我慢しました。
そんなリューイをよそに、おばあちゃんは二人に優しく聞き返しました。
「私たちの国って、妖精の国のこと?」
二人はやれやれというように肩を竦めてみせました。
「妖精の国ですって?」
「そんな国、あるわけないでしょ。」
どうやら、妖精というのは、かなり失礼な生き物のようです。さすがに今度ばかりは、リューイも憮然とした表情を隠そうともしませんでした。おばあちゃんはリューイを宥めるように頭を優しく撫でると、リューイに代わって妖精たちに質問し始めました。
「私たちはドラゴンのこと、何も知らないのよ。どうしたらいいか、教えてくれないかしら?」「しょうがないわね。」
「特別よ。」
二人はおばあちゃんの右の肩と左の肩にそれぞれとまりました。
「あら、なんだか良い匂いがするわ。」
「本当だ!美味しいそうな匂い!」
妖精たちはおばあちゃんのふわふわした薄茶色の髪に顔を埋めると、盛んに匂いを嗅ぎ始めました。おばあちゃんはくすぐったそうにしています。
「くんくん、これは小麦粉とバターの匂いね。」
「むむっ!チョコレートの匂いもするわ!」
「ちょっと二人とも止めて。くすぐったいでしょ。」
両側からくんくんされて、おばあちゃんはくすぐったさに肩を竦めました。
――どうやら、二人とも相当の食いしん坊さんみたいね。後でクッキーを食べさせてあげなくちゃ。
おばあちゃんは今朝、焼いたクッキーを思い出しました。
おばあちゃんが赤ちゃんドラゴンの上に掛けてあった白い布をそっとめくると、妖精たちが両側から覗き込みました。ときどき、そっと赤ちゃんドラゴンを触ってみたり、押してみたりしますが、赤ちゃんドラゴンはぐったりと横たわったまま何の反応も示しません。
「体が冷たいわ。」
「ぐったりしているね。」
赤ちゃんドラゴンが思ったよりも弱っていたので、妖精たちは焦りました。すぐに餌を取ってきて、食べさせなければなりません。しかし、これだけ弱っていると、餌を食べられるかどうかも怪しいものです。
赤ちゃんドラゴンは小川の畔に捨てられてからずっと一人で不安や恐怖、孤独と闘ってきたのでしょう。一瞬たりとも気を抜けない環境の中で、まだ目も開かない赤ちゃん竜がどうして何かを食べようとするでしょうか。残念ながら、この人間たちが赤ちゃんドラゴンを救えるとは思えません。この子に餌を食べさせる前に、まずはこの子を安心させてあげなければなりません。
妖精たちは考えました。この子は卵の頃から孤独とは無縁の環境で育てられてきたのです。母竜や愛する人たちと離れ、遠い異国の地で、小さい体を丸めてじっと耐えているこの子に、今、一番必要なものは何でしょうか。
気が付けば、二人は今の赤ちゃんドラゴンに500年前の自分たちを重ね合わせていました。あれは二人がまだ緑の谷に棲んでいたときのことです。
静かな谷間の妖精王国は、人間たちの手によって一瞬で滅んでしまいました。何百人もいた妖精たちの中で生き残ったのはたった二人だけ。棲み家を失ったキキとリンは、群れからはぐれた羊が野の獣に追われるように、あてもなく彷徨い続けました。
あの頃のことは辛すぎて、記憶には霞がかかっています。ただ一つだけ確かなことは、二人を愛してくれた人たちの思いが、あの頃の二人を生かしていたということ実です。どんなに苦しくても人生は続くのです。自分で自分の人生を終わらせないこと――それが生き残った自分たちに課せられた義務だと二人は思いました。
二人は来る日も来る日も悲しみや喪失感、恐怖や孤独やと闘い続けましたが、そういった感情は一日や二日でなくなるものではありませんでした。長い歳月を経て、やっと少しずつ忘れることができるようになってきたのです。
ある日、二人は長い放浪の末、羊飼いの国に辿り着きました。気持ちの良い草原の風に吹かれて二人が休んでいると、どこからともなく遊牧民の少女が歌う素朴な歌が聞こえてきました。どこか懐かしいその響きに、二人は一瞬にして過去へと連れ戻されました。
二人の目の前に浮かび上がった妖精王国では、疾うの昔に亡くなった人々が笑い、歌い、踊っていました。妖精族は平和を愛する陽気な民でした。歌と踊りとおしゃべりといたずらが大好きで、彼らの中には争いことがまったくありませんでした。また、妬みや憎しみ、殺人や偽りもありませんでした。誰かが誰かより偉いわけでもなく、皆、平等でした。彼らは非常に勤勉でしたので、金と銀、そして様々な財宝を持っていましたが、富に執着することもなければ、一人占めしようとする者もありませんでした。そのため、着る物のない人、餓えている人、貧しい人や病気の人が見過ごしにされることはありませんでした。また、老いた者でも若い者でも男でも女でも、助けを必要としている人々には偏りなく、それぞれが自分の持っている分に応じて惜しみなく持ち物を分け与えました。また、白妖精族とか青妖精族とか言われる者はなく、彼らは一つであり、皆、王国を受け継ぐ者でした。神の手で造られた者の中で、彼ら以上に幸せな民はありませんでした。
少女が羊を追いながら丘の向こうへ消えてしまうと、妖精王国の幻もいつの間にか消え、目の前にはただ、どこまでも広がる草原が続くばかりでした。夢でも見ていたのでしょうか。
まだ夢から覚めやらぬ様子のキキの傍らで、リンがふと、一つの歌を歌い出しました。それは妖精たちの子守歌でした。悲しい内容のその歌は、妖精の国ではなぜか昔から子守歌とされており、二人もこの歌を聞いて育ってきました。
リンの深みにあるアルトにキキの透き通ったソプラノが重なります。歌い終わったとき、二人は抱き合って泣きました。二人はもう何年も歌を歌うことすら忘れていたことを思い出しました。ただ生きていただけ――いつ死んでも構わないと思っていたの二人が、初めて「生きよう」と思った瞬間でした。
この赤ちゃんドラゴンだって、こんな形で命の灯を消してよいはずがありません。この子の家族のためにも、また、この子を愛してくれた人たちのためにも、生きなければならないのです。気が付けば、二人は自然に子守歌を口ずさんでいました。
風よ、聞かせておくれ
あの歌を
優しい膝の上で聞いたあの歌を
草原よ、歌っておくれ
あの人が好きだった歌を
私が愛したあの人はもういない
空の下に宿り、木に枕にする旅人のように
私には帰る場所がない
それでも私は歌う
故郷の歌を
愛する人たちのために
父よ、母よ、妹よ
どうか私を見守っていて
天でまた会うその日まで
二人の歌を聞いていつの間にかこの歌を覚えてしまった青の国の女王も、卵が入ったゆりカゴを揺らしながらいつもこの歌を歌っていました。
妖精たちが歌い始めると、部屋の中の空気ががらりと変わり、深い安らぎに満たされました。異国の言葉で歌われたので、リューイたちには歌の意味はわかりませんでしたが、なぜか涙が止まらなくなりました。おばあちゃんは思わずエプロンで目頭を押さえました。
妖精たちが歌い始めて暫くすると、静かだったカゴの中からミュウミュウと小さく鳴く声が聞こえ始めました。その声は次第に大きくなり、やがて赤ちゃんドラゴンは自ら白い布を押しのけてカゴから顔を出しました。まだ、何も食べていないのに少し元気になったように見えます。
――妖精たちの温かい心が通じたのかしら。
おばあちゃんは涙を拭うと、二人に微笑みかけました。
「二人とも本当に歌がお上手ね!感動したわ。」
おばあちゃんが小さく拍手をすると、妖精たちは照れたようにもじもじしました。
「うふふ、そんなことないわよ。ねえ?」
「ねえ。」
二人は満更でもない様子で、顔を見合わせました。そして褒められたことが照れくさかったか、話題を変えるようにこう言いました。
「えっと…それより、この子は何を食べるのか知りたいんだったわよね?」
「そうそう!」
おばあちゃんは思い出したとでも言うように、手の平に拳をポンと打ち付けました。
「赤ちゃんドラゴンは…」
妖精たちは、小さな子供にでも説明するかのようにゆっくりと話し始めました。


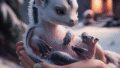
コメント