皆が一安心したところで、おばあちゃんはユストの濡れた服を見遣りました。このままでは風邪をひいてしまいます。見たところ、ユストは背丈がおじいちゃんと同じくらいのようでした。おばあちゃんはユストの為に着替えと温かいお風呂を準備することにしました。
ユストは着替えを貸してもらえるだけでも十分、有難いと思いましたが、おばあちゃんが「風邪をひかれては困ります」と言い張るので、好意に甘えて風呂も借りることにしました。
ユストにとって嬉しい誤算だったのは、バスタブがおじいちゃんの体に合わせて大き目にできていたことでした。お蔭で長身のユストでも脚を伸ばして湯に浸かることができました。
暖かいとはいえ、季節は既に初秋です。濡れた身体はすっかり冷え切っていました。長旅の疲れも溜まっています。正直、温かい風呂は最高のご馳走でした。
湯から上がると、ユストは用意されていた着替えを身に付けました。保存状態が良いのか、おじいちゃんの服は洗い立てのようにさっぱりとしていました。袖を通すときに一瞬、樟脳の匂いと共に日向臭い年寄りの匂いがしましたが、長年、モルデカイと一緒に暮らしてきたユストにとっては、それは不快な匂いではありませんでした。むしろ、どこか安心する匂いでした。
――きっと優しい人だったんだろうな。
何となくそんな気がしました。
「お蔭様で生き返った気がします。とても気持ちが良いお風呂でした。お心遣い痛み入ります。」ユストは風呂から上がると、丁重にお礼を述べました。
「いえ、いえ、お礼を言うのはこちらのほうですよ。猫を助けてくれてありがとうございました。」
おばあちゃんはユストを見上げると、顔を綻ばせました。
「ぴったりですね!サイズはどうですか。」
「調度いいみたいです。ありがとうございます。」
おじいちゃんの服は誂えたようにぴったりでした。木こりをしていたおじいちゃんはユストよりも逞しかったのですが、背丈や手足の長さはほぼ同じで、袖や裾を折り返す必要もありませんでした。
「ユストさんは本当に背が高いのね。あの人の服はウチの息子ですら大き過ぎて着られないんですよ。身長はどのくらいあるの?」
「198㎝です。」
「そうでしょう。そうでしょう。あの人もそのくらいでしたよ。」
おばあちゃんはニコニコしていました。
おばあちゃんが淹れてくれた温かいお茶を飲みながら、ユストは赤ちゃん竜が小川の畔に捨てられた経緯を話してくれました。
「あれの母親は白竜という種類の小型のドラゴンです。小さい頃に青の森で女王に拾われました。白竜は元来、気性が穏やかなドラゴンですので、彼の母親は女王の遊び相手として城で飼われることになりました。幸いにも城の中にはドラゴンを飼うだけの十分なスペースもありました。」
そう言うと、ユストは遠くを見るような目をしました。
白竜を拾った日、まだ幼かった女王は真っ先にユストにその子を見せてくれました。
キュピッ!?
女王の腕の中から人懐っこい目で見上げる白竜の子に、ユストのハートは一瞬で撃ち抜かれました。
――はうっ!な、なんて、可愛いっ!
白竜の子は人間に対する警戒心が全くないようで、女王の腕の中でじっとしていました。ユストが頭を撫でてあげると、気持ちが良いのか無音に近い鳴き声を発しました。
――クルルッ
あの頃は二人とも無邪気でした。二人で笑い合い、走り回った日々をユストは懐かしく思い出しました。こんな日が来るなんて、夢にも思いませんでした。

「白竜は翼もなく、空も飛べないため、青の国から外へ出たことはありませんでした。しかし、ある日、一頭の青竜が我が国に迷い込んで来て、二人は出会い、恋に落ちました。我が国には湖がたくさんありますので、彼の父親はそれに誘われてやって来たのでしょう。恐らくはキミラ国か、または北方のカラン国辺りからやって来たのだと思います。ご存知かもしれませんが、カラン国は遥か北方にある氷と水に閉ざされた国です。」
もちろん、リューイもおばあちゃんもそんな国はご存知ありませんでした。
「そして、彼が生まれたのがつい半年ほど前のことです。彼は白竜と青竜の混血ですし、雄ですから、体は母竜よりも大きくなると思います。しかし、実際のところ…」
ユストはそこで一旦、言葉を切りました。そして少し考え込んでから、こう話を続けました。
「私どもには彼がどのようなドラゴンになるのか、見当もつかないのです。なにしろ、白竜と青竜のミックスを見たのは私たちも初めてですから。父親の血を引けば空を飛べるようになるかもしれませんし、母親の血が濃ければ翼があっても飛べないかもしれません。」
ユストはリューイに視線を移すと、リューイの瞳の奥を覗き込むようにしました。
「青竜は肉食ですが身体が小さいうちは肉を与えず、草食獣として育ててください。肉を与えないほうが気性も穏やかになり、人間とも暮らし易いはずです。」
ユストの話によると、ドラゴンが沢山いたとき代には、竜は種族に従って分かれて生活していたので血は混じり合わなかったようです。しかし、竜の数が減少するにつれて、次第に血が混じり合い、新しい種が生まれるようになったそうです。

ユストは懐から白い布を取り出しました。
「それから、これはあのカゴの中の中に入っていた布ですが…」
「あっ!」
ユストが言い終わらないうちに、リューイは叫びました。
「これっ!見たことある!思い出した!」
リューイは突然、あの不思議な夢を思い出しました。夢の中に出てきた女の人は、この白い布を握り締めて泣いていました。今の今まで夢を見たことさえ忘れていたというのに、ユストに白い布を見せられた途端、今しがた夢から覚めたばかりように記憶がありありと蘇りました。
よく見ると、白い布の四隅には青い糸で飾り文字が刺繍されていました。イニシャルのようでしたが、リューイにはよくわかりませんでした。
リューイがユストに夢の話をすると、ユストは黙って頷きました。そして暫く何かを考え込んでいました。
「やはり、リューイさんとあの子には浅からぬ因縁があるようですね。」
ユストは何か納得したようでした。


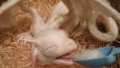
コメント